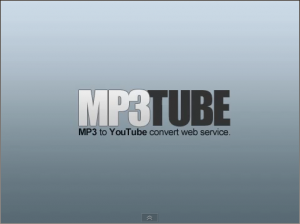カッターヘッド製作
garage nakamuraです。
私が使っているシートカッターは、ミラとかミラーと呼ばれていて内燃機加工関係の所では一番ポピュラーな物だと思います。
電動の物と手動の物と有るのですが、私の使っているのは手動の方です。
本とは電動の物が欲しいのですが、とても私の経済状況では買えないです...^^;
最近はこのミラ製ばかりでは無くサーディー(フランスかな?)等のシートカッターを導入している所も有るようですが、
機械本体の画像を見るだけでもとても買えそうに無いので値段も調べて居ません。笑
使い方も<使う人の腕ですね!
も有るのでしょうが、特に私が使っているミラの手動の物は使い方が難しいです。
センターを出して削り始めるまでは比較的簡単なのですが、深く削りこんで行くうちに本体の剛性が無いからでしょうか?微妙にズレが出てきてしまいます。
ですから、ちょっとでも切れ味が悪くなるようならば直ぐに追い込むのを止めてセンターが狂っていないか?再検査しないと綺麗な当たりが出なくなってしまいます。
もうちょっと簡単に正確に追い込めないかとず~っと考えていて以前に一度カッターヘッドだけを作ったのですが、やっとの思いで作ってみたら見事に失敗でした。^^;
このヘッドだけでも以前聞いた時には8万円とか10万円とか聞いていたのでとても簡単には買えませんね!
別に今使っているヘッドが駄目になっているのでは無くて、別の機械に付けて使いたいと思っているので、
もし新品を買っても加工してしまいますから勿体無いですし、何とか作れそうなんですね。
材料代だけなら全然安いですから余っていた材料で作ってみたのが↑の画像です。
今回はサイズ(寸法)はOKです。
材質がS45Cと言う一般的に使われている材料である程度の硬さは有るのでそのまま使おうかと思ったのですが、
シートカッターに使われている物は熱処理がして有るんですね。
少しは熱処理の勉強をしたのでここは一つやってみましょう!と言う事で始めたのですが、後悔先に立たずを経験する羽目になってしまいました。
続くです...(-_-;)